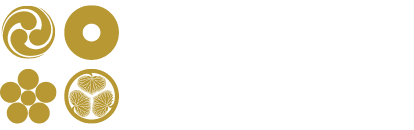松山城二之丸史跡庭園は、表御殿跡と奥御殿跡に大別されます。表御殿跡は北半分にある「柑橘・草花園」で、各地のカンキツ類や草花で昔の部屋の間取りを表現しています。奥御殿跡は西南部にある「流水園」で水と砂利と芝生で昔の部屋の間取りを表現しています。東側の「林泉庭」は、露岩を背景にした池や滝を配置して「わび」、「さび」を表現しています。
発掘によって、その規模や大きさが注目された大井戸遺構は、そのまま露出展示しています。
庭園内には有料施設としてご利用いただける、「観恒亭」、「聚楽亭」、「勝山亭」があります。
二之丸御殿の構成
松山城二之丸史跡庭園は、藩の中枢としての役割を果たす表御殿と藩主の家族の住居、奥御殿からなり、北側の四脚御門を公式の門とし、足軽などの詰所である御徒歩番所、応接座敷である御広間、書院、その他公式儀礼の間と続きます。
西側の多聞櫓の門は通用口で、その奥には奥向きの居室や台所・炊事の土間の類が建ち並びます。
藩主の御居間は東南の日当たりの良い区域に設けられ、御居間と書院との間には黒炬燵之間、柳之御間、棕櫚之御間それに続き鎖之御間、御数奇屋と茶室も備わっています。

大井戸遺構

露出していたのは西半分だけで、東半分はいろりで火をおこしていた「焚火之間」が覆っており、その基礎部分が残存しています。
石段を上ったところにある一段低いところが床下通路跡で、火災の際、木桶で水をくみ上げ、地下通路を経て運搬していたものと考えられます。
水琴窟

江戸初期の茶人・建築家・造園家である小堀遠州により考案されたという造園技術の最高傑作です。
水滴の量、瓶の大きさ・質・焼き方、周りに埋めるグリ石など、様々な条件によって音色が変わるため、一つとして同じ水琴窟はないといいます。また,同じ水琴窟でも、時間帯や季節によって音色が異なります。
水滴が地中の瓶を通って、受皿に落ち、反響する音に魅了される人も多いようです。
多聞櫓
櫓はもともと「矢倉」と書いて、武器庫でしたが、後に城の防衛や反撃の拠点として機能するようになりました。
櫓は城を囲む塀の上に小屋を乗せたようなものですが、多聞櫓は石垣の上に沿って長く続いています。松永久秀が大和に築いた多聞山城に初めて造ったことから、多聞櫓と呼ばれるようになったと考えられています。
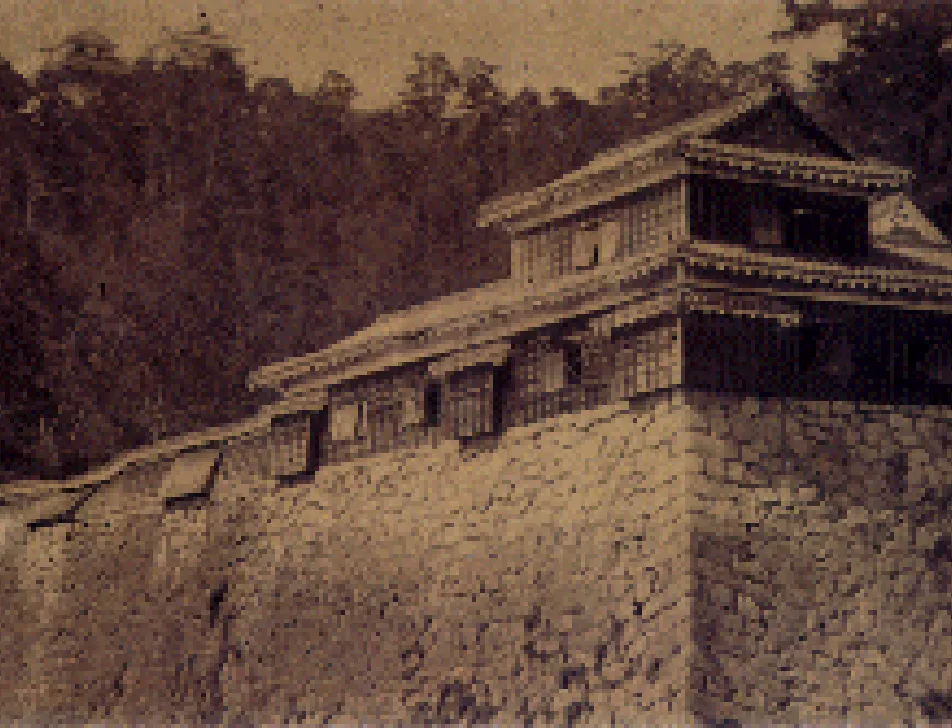

狭間

外向きには小さく、内向きには広くなっている窓も防衛のためです。
縦長の長方形が矢狭間で、正方形が鉄砲狭間です。
石落とし

石垣から張り出した床の空間から、石などを落とすための防衛設備。
迫ってきた敵兵はもちろん、石垣に飛散した石が周囲の兵隊にも打撃を与えます。
四脚御門

藩主の御殿や有力家臣の屋敷、政務の施設など、藩政の舞台として機能していた。現在は一部埋め立てられているが、築城時にはほぼ全域が水堀で囲まれていた。
井戸屋形

井戸を保護し、水を汲む人を日照りや風雨から守るための建物。
米蔵

築城当初は勘定部屋とされていましたが、松平期後半には塩や味噌を貯めておく蔵となっていました。
藩邸が二之丸から三之丸に移行し、二之丸の政治的機能が低下した一つの証拠とされます。
御居間

日当たりの良い東南に位置しており、御居間(一の間)、次御間(二の間)、三の御間と縦に並び、真ん中の次御間に御帳台が隣接。
通常、居間は殿様のプライベートルームですが、御帳台の存在から、次御間では家臣との接見も行い、御居間のみ完全なプライベートルームだったと思われます。
大書院跡

古絵図によると御帳台と呼ばれる座敷飾りが設けられています。自分の座っている間が相手より一段高く、周りに豪華な装飾を施した応接座敷で、他者との身分格差を誇示するために作られたものです。
親藩松平家の高い格式を強調するため、改築されたものとされています。
書院は御殿で最も重要な公式儀礼の場で、学問の講義・能・仕舞・連歌会・具足披露などの行事がありました。
恋人の聖地
松山城二之丸史跡庭園は、2013年10月1日「恋人の聖地」として、NPO法人地域活性化支援センターに選定されました。これは、和風情緒のある景観に加え、日露戦争時のロシア人捕虜の男性と日本人女性看護師のロマンスを秘めた金貨が出土したことと、結婚式の前撮りの場所として、年間700件ほどの撮影が行われていることなどが評価されたことによります。


恋人の聖地 ご来園のカップル様へ
誓いのメッセージカードに普段言えない思いを託しませんか?
ご来園入園のカップル(2名1組様)の中からご希望の方に、『誓いのメッセージ』を記入して頂き、庭園内に掲示。さらに、松山城ホームページのブログにも掲載いたします。
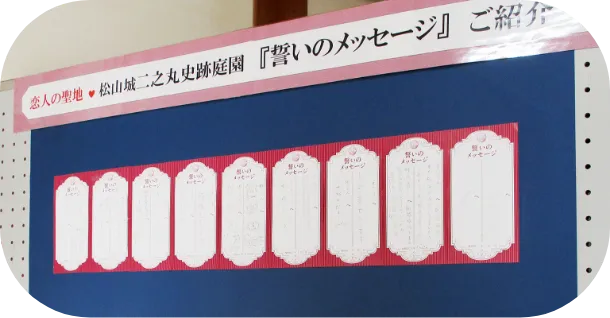
恋人の聖地プロジェクトの趣旨
NPO法人地域活性化支援センターでは「少子化対策と地域の活性化への貢献」をテーマとした『観光地域の広域連携』を目的に「恋人の聖地プロジェクト」を展開しています。
恋人の聖地プロジェクトでは、2006年4月1日より、全国の観光地域の中からプロポーズにふさわしいロマンティックなスポットを「恋人の聖地」として選定し、地域の新たな魅力づくりと情報発信を図るとともに、地域間の連携による活性化を図っています。
また、このプロジェクトでは「非婚化・未婚化の進行」を少子化問題のひとつとして捉え、全国各地で選定された100ヶ所を超える「恋人の聖地」とともに、フランスのモン・サン・ミッシェルをはじめ海外の著名な観光地にも参画いただき、各地域による様々な活動を通して若い人々のみならず「結婚」に対する明るい希望を持った地域社会に向けた空気の醸成を図るための活動をしています。
基本情報
| 名称 | 松山城二之丸史跡庭園 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市丸之内 |
| 営業時間・ 観覧料 |
|
| 認定 |